人力で世界を巡るという大規模なチャレンジは、冒険好きな人にとっては一度は夢見る目標でしょう。
では、実際にその偉業を成し遂げるにはいったい何日ほどかかるのでしょうか。
本記事では、地球の周長から歩行ペースの目安を算出し、他の交通手段を用いた場合との時間差、実際に徒歩で世界一周を成し遂げた人々のエピソードやコース選定のポイント、必要な装備や健康管理の重要性などを多角的に解説します。
これらを踏まえ、徒歩で世界一周がどれほど実現可能なのか、具体的な視点から考えていきましょう。
1. 地球の周長をどう測る? その計算の仕組み
地球一周の基本的な長さを把握する
地球を「一周」するといっても、どの位置をぐるりと回るかによって長さはわずかに変化します。
- 赤道ベース:最も長い周囲で約40,075km
- 極を通るパターン:わずかに短く、約40,008km
さらに実際の地形や標高差を考慮すると、実測値に差が出る場合があります。
赤道を基準とした数値
赤道の一周がおよそ40,075kmと算出されているのは、人工衛星を使った正確な測定によるものです。
- わずかな楕円形状ゆえ、場所によって計測結果はわずかに変化
- 現在はGPSなどが普及し、高精度な値がわかる
測定方法で変わる数値の違い
- 地上での調査:山や谷など起伏が多いと総距離が増える
- 衛星を活用した測定:想定上の平面データを扱うこともあり、実際に歩く距離とは異なる
徒歩で回る場合、実際には平坦路だけでは済まないため、単純な数字以上の距離を要するでしょう。
2. 徒歩世界一周に必要な時間とは
歩行速度をもとに概算を出す
人が普通に歩く速度は、だいたい時速4~5km前後といわれます。
- 時速5kmで歩く → 1時間で5km
- 24時間フル稼働の理想値 → 1日120km
とはいえ休憩や食事を考慮しなければならず、実践ではこの値を保つのは困難でしょう。
1日あたりの歩行距離で試算
たとえば、1日8時間だけ歩くと仮定すると以下の計算になります。
- 5km/h × 8時間 = 40km/日
- 40,075km ÷ 40km/日 = 約1,000日(約2.7年)
ただし、これは平坦でトラブルのないコースを進める想定での数字。
国境手続きや地形の変化、悪天候、体調不良などを踏まえると、より長期化するのが一般的です。
実際の行程で考えられるハードル
- 山岳地帯や荒れた道路:歩行ペースが大幅に低下
- 気候・環境要因:極端に暑い・寒い地域では休息も多く必要
- 装備の負担:テントや食料を背負うとスピードも落ちる
こうした要因から、3年~4年以上かけて世界を回る冒険家も珍しくありません。
3. 車や船と比較した場合にかかる期間
自動車で巡る世界一周の目安
舗装路を前提に、車が時速100kmで移動可能とします。
- 40,075km ÷ 100km/h = 約400時間(約16~17日)
- しかし、海を渡るには船や飛行機が不可欠
- 国境やビザの手続き次第で、所要時間は大きく変動
さらに、地域によっては整備された道路がない場合もあるため、実際には理想どおりにはいきません。
クルーズと徒歩ではどう違うか
世界一周クルーズのプランは、80日~150日程度が一般的です。
- 高速の直行便:短い日数で一周可能
- 観光寄港が多い場合:その分、日数が増加
- 天候や航路によって日程の変更もあり
船旅ならではの寄港地観光や海を楽しむ時間が多い一方、徒歩や陸路ではアクセス不能な地域にも行ける利点があります。
移動手段を組み合わせる発想
- 徒歩×自転車:町間の距離が長い場所で使い分ける
- 公共交通機関の活用:連絡バスや鉄道で一部を短縮
- 予測不能な状況:天候の急変や災害、情勢不安が起きたら柔軟な対応
すべてを徒歩にこだわらず、状況に合わせて移動手段を切り替えることで、長旅を快適にする選択肢が広がるでしょう。
4. 過去に世界一周を成し遂げた人たち
歴史的に最初に成功した例
地理上の「世界一周」として有名なのは、マゼラン艦隊(1519~1522年)が最初とされます。マゼラン自身は途中で命を落としましたが、艦隊の一部が地球を一周して帰還したという歴史的快挙が残っています。
徒歩で達成した冒険家の事例
実際に徒歩で世界を回った人も少数ながら存在します。
- 1970年代にはデイブ・クンストが歩き通した記録が有名
- 多くの困難を乗り越えながらも、各地で人々の支援を得ることで達成
長距離旅を実現させるコツ
- 装備の選定:荷物を必要最低限に絞る
- 食料計画:栄養バランスを意識しつつ補給ルートを確保
- 健康管理:感染症予防や怪我への対処法を学ぶ
過去の冒険家たちは、物理的にも精神的にも綿密な準備と対応力が成功を支えています。
5. 日本からのルート設計と注意点
国内発着で考えるプラン立案
日本からスタートして徒歩で世界を回るには、まず隣国へ渡るフェリー路線などを検討するのが一般的です。
- 韓国・ロシア方面:航路が比較的利用しやすい
- 各国の入国条件:ビザ取得や出入国管理の手間を事前に調べる
海路を超えた先で、どのようにルートをつなぐかが鍵となります。
極地や赤道をどこまで含むか
- 赤道付近:熱帯性気候による降雨や高温・高湿度の対策が必要
- 北極や南極に近いルート:極寒と氷雪の影響で装備や体力の要求水準が格段に上昇
また、ユーラシア大陸やアメリカ大陸をどこからどこまで縦断するかでも、移動距離やビザ要件が左右されます。
GPSを使った移動管理の利点
- 正確な位置情報:迷いやすい道でもリアルタイムでルート確認
- 進捗管理:1日の移動距離や到達地点を常にチェック
- 緊急時の対応:通信可能な環境下なら、位置情報を誰かに共有して安全を確保
ただし、バッテリー消費や機器故障のリスクもあるため、地図やコンパスなどアナログツールを併用することも大切です。
6. エラトステネスが示した地球の大きさ
先駆的な地球円周の推定方法
紀元前3世紀に、エラトステネスは太陽光の角度差を活用して地球の周長を概算しました。驚くほど正確に近い値を導き出したことで有名です。
直径と円周の関係性
- 地球の直径:約12,742km
- 円周:直径 × 3.14(π)の概算で、4万km前後に相当
現代では人工衛星やGPSを通じて、エラトステネスの推論がいかに的を射ていたかが確かめられています。
古代の知識と現代科学の比較
古代ギリシャ時代にも高度な数学的アプローチが存在し、それが現在の最先端技術による測定結果とほぼ合致している事実は、天文学や測量技術の歴史を考えるうえでも興味深いポイントです。
7. 徒歩で移動する際の留意事項
長期歩行の健康・体力管理
- 栄養管理:携帯食や水分補給がとても重要
- 休息と睡眠:定期的に体を休めることが歩行能力を維持するコツ
- ストレッチや軽度の筋トレ:疲労回復や怪我の予防に効果的
体調不良が起こると旅程に大幅な遅れが生じるだけでなく、命にかかわるケースもあります。
装備品の選び方と安全確保
- GPSや地図:道に迷わないための必需品
- 応急処置キット:外傷や体調不良に即対応
- 防犯対策:高価そうな荷物は目立たないようにし、貴重品は分散して持つ
また、土地によっては野生動物や治安面のリスクもあるため、事前に安全情報を収集し、場合によっては地元ガイドを頼る判断が必要となるでしょう。
歩くからこそ味わえる魅力
- 景色の変化をじっくり堪能:車や電車では気づかない細部にも目が届く
- 現地の人との交流:ゆったり歩く分、コミュニケーションの機会が増える
- 四季や風土を体感:スピードを落とすほど、地域特有の美しさが見えてくる
徒歩旅ならではの「そこにしかない発見」に出会えるのが醍醐味です。
8. 多様な文化と地域差がもたらす旅の面白さ
各地域で出会う異文化との触れ合い
歩みを進めるにつれ、言語や食文化、宗教や習慣ががらりと変化します。
- ローカルフード:その土地ならではの味を堪能
- 伝統行事や祭り:タイミングが合えば現地のイベントを体験可能
- 人との出会い:地元の人々の温かさを感じる機会が増える
地形と気候がもたらす歩行条件の変化
- 暑い砂漠地帯:水の管理が生命線
- 寒冷地や山岳エリア:装備の防寒性能が必須
- 熱帯雨林:降雨で足元が悪くなるだけでなく、虫や動物対策も必要
日本との違いを楽しむ視点
国境を越えるごとに、建築様式や交通ルール、生活リズムが変わるのも楽しさの一つ。徒歩での旅はこうした違いを肌で感じる絶好の機会と言えます。
9. 実際の速度に基づく具体的な計算例
条件設定を反映した現実的な日数試算
平地を中心に天候も安定している場合と、荒天や標高差の激しい地帯を含む場合では、数字が大きく変動します。
- フラット路中心:1日50km以上も十分あり得る
- 山岳・砂漠混在:1日数十kmに満たない日も
過去のデータを活用するメリット
- 実際の冒険家の歩行日程:どの地域を何日かけて通過したか
- 季節ごとのコンディション:ベストシーズンを狙うか、敢えてオフシーズンに挑むか
- 補給や宿泊:事前に計画しておけば緊急事態も回避しやすい
現場で得られる生きた情報を調べておくと、より現実的なプランニングが可能です。
旅程の計画を可視化する方法
- GPSログ:進んだルートを記録し、ペースの把握に役立てる
- シミュレーションソフト:高低差や気候条件を反映させ、到着日を想定
- スプレッドシート:日ごとに必要な距離や休息日を明記し、スケジュールを組む
こうした手法で、地球一周にどれだけの時間がかかるかを「見える化」でき、モチベーション維持にも効果があります。
10. まとめ
徒歩で地球を一周しようとするなら、単純計算では2~3年程度で可能ですが、現実にはさらに長期化する場合が多いでしょう。天候や地形、国ごとの手続き、体力の維持など、多様な要素が絡み合うからです。
しかし、それだけに得られるものも大きく、世界の人々や多文化に触れ合いながらの長旅は、人生を深めるきっかけになるはずです。足の力だけで地球を回る挑戦は、一見すると過酷に見えますが、じっくりと歩みを進めることでこそ見える風景や出会いが待っています。
- 時間やリソースを綿密に計画
- 健康面・装備面での備えを万全に
- 文化や人々との触れ合いを大切に
「歩いて地球を一周する」という壮大な目標は、行程の長さだけでなく、その過程の経験こそがかけがえのない財産になるでしょう。旅の意味や持続可能な移動手段としての意義を再考するうえでも、大いに価値のある挑戦だと言えます。

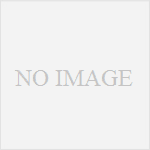
コメント